
「KOBE ART MARCHÉ」と同時開催される公募展「Artist meets Art Fair」は、若手アーティストの新たなステージへの挑戦を後押しするプログラムとして開催を重ね、多くのアーティストが、神戸から広いアートマーケットの世界へと羽ばたいていきました。
本記事では、「Artist meets Art Fair」入選者たちが、当時どんな思いで応募に踏み出し、そして、その後どのような道を歩んでいるのかをご紹介していきます。
今回は、2024年開催の第9回「Artist meets Art Fair」一般枠で入選し、オーディエンス賞を受賞された西村 祐馬さんにお話を伺いました。
応募に至った背景、入選作について、そして応募を検討している方へのメッセージなど、さまざまなお話をお聞きしました。
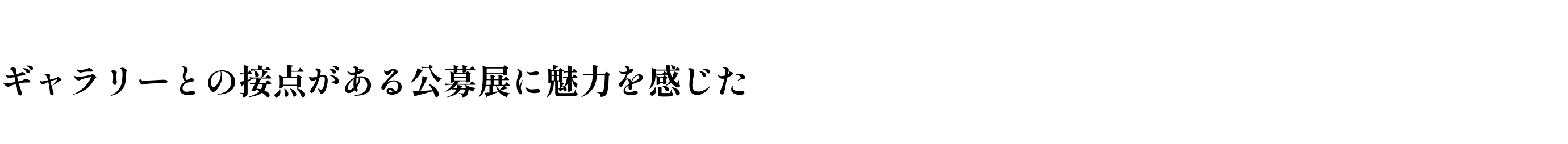
- 「Artist meets Art Fair」に応募されたきっかけを教えてください。
- アーティストとして本格的に活動を始めたのは、2023年4月ごろからです。活動を始めてから、公募展の情報は常にチェックして意識するようにしていました。そんな中でたまたま目に入ったのが「Artist meets Art Fair」でした。応募したのは2024年です。
応募を決めた一番の理由は、ギャラリーとの接点がある点です。以前ギャラリーで働いていた経験もあり、出展ギャラリーの中に実際に知っているギャラリーの名前が並んでいたことで安心感がありました。
単に展示の機会が得られるだけでなく、その先につながる可能性が感じられたことが、応募を後押ししてくれました。

- 入選作品について、コンセプトや制作時の思いを教えて下さい。
- 現代はビジュアルが主軸となり、既視感のあるイメージが溢れています。しかし、頭で理解するスピードに身体が追いつかず、どこか「身体が置き去りにされている」という感覚を抱いてきました。
この問いに向き合う原点となったのは、祖父の死に際し、その遺体に触れた経験です。視覚を超えて身体に深く刻まれた「触覚の記憶」を、いかに作品として留めるか。それが私の制作の出発点となりました。
アート、特に写真は本来、鑑賞者との間に物理的な距離があるメディアです。その距離を縮め、イメージを「もの(マテリアル)」として定着させるために、私は支持体として「ヌメ革」を選びました。日常的な革に、あえて人間の身体をプリントする。そこに生まれる違和感やおどろおどろしさを通じて、鑑賞者の感覚や記憶を揺さぶりたいと考えたのです。

- 「KOBE ART MARCHÉ」での展示で、印象的な出来事はありますか?
- 会場では、実際に多くの方に作品に触れてもらいました。「美術作品には触れてはいけない」という前提があるからこそ、あえて触れることで生まれる作家と鑑賞者の共有体験が、深い理解やセールスに繋がったと感じています。
特に印象的だったのは、タイから来られた女性です。祖母の皮膚を写した作品に触れた瞬間、大切な方を亡くされたばかりだった彼女は涙を流されました。触れることで記憶や感情が呼び起こされる――その瞬間に立ち会えたことは、作家として大きな糧となりました。
AIがどれほど進化しても、触れることによる悲しみや痛みを「実感」することはできません。他者の記憶に共鳴し、心動かされることこそが、人間である証なのだと改めて強く感じています。
- KOBE ART MARCHÉを経て、新たな展開はありましたか?
- 会期中、中国のギャラリーの方が会場を訪れてくださり、名刺交換をしました。その後、今年の前半に改めて声をかけていただき、作品を中国のアートフェア「West Bund Art & Design」に出品することになりました。
もともと制作していた3点に新作2点を加え、計5点を出品し、結果としてすべて完売しました。今後は香港のアートフェアへの出品も予定しており、とても良い機会を得られたと感じています。
「Artist meets Art Fair」に応募した当初の目的であった、「ギャラリーと出会い、次につながるきっかけをつくる」という点については、ひとつの達成感があります。
今後も焦らず、一つひとつの機会で作品を丁寧に見せながら、種をまくように関係性を育てていきたいと思っています。

- アーティスト活動以外でもご活躍されていらっしゃいます。現在のご活動について教えて下さい。
- 現在、写真専門のアートフェアの運営(PM)を担当しています。
アジアにおいて写真作品を販売するハードルは依然として高いのが現状です。多くの人が見に来ても、購入に繋がるケースは極めて少ない。その中で「作家として生き残る」ためには、自分自身の制作だけでなく、活動の土壌となる“市場そのもの”を広げる必要があると考えたのが、関わることになったきっかけです。
フランスの「Paris Photo」のように、写真を取り巻く文化が成熟した場を日本でも作りたい。写真は「この一枚が好き」という直感で選びやすく、ファーストコレクションとしても最適です。そうした入り口を増やすため、現在は運営の視点から市場のボトムアップに取り組んでいます。
グラフィックデザイナー出身ということもあり、私は物事を俯瞰して捉える傾向があります。アーティストとして評価されないときは「需要が足りないだけ」と割り切り、どこに人の流れを作れるかを考える。個人戦ではなく、アーティスト、ギャラリー、フェアが連帯する「団体戦」として市場を動かしていくことに、今は大きな意義を感じています。

- 今後の展望について教えていただけますか?
- 海外での滞在制作(アーティストインレジデンス)には今後も注力したいです。直近ではフィンランドを訪れ、過去10年分の思考を焚き火で燃やすという、ある種「情報のデトックス」を行いました。物理的には手放し、必要な栄養だけを取り込んで次へ進む。焚き火という文化が国全体に浸透しているのが新鮮な感覚でした。次は、死をポジティブに捉える文化のあるメキシコに惹かれています。
制作においては、「作りたい」という気持ち(ゲージ)が十分に溜まったときにだけ体が動く感覚を大切にしています。生産性を追い求めるのではなく、自分の内なる欲求と社会の視点、その中間地点で生まれる「一点もの」を丁寧に形にしていきたいですね。
ジェネラリストとして多方面で活動する自分がどう評価されるかは分かりませんが、これからも自分にしかできない歩みで、誠実に活動を続けていきたいと思っています。
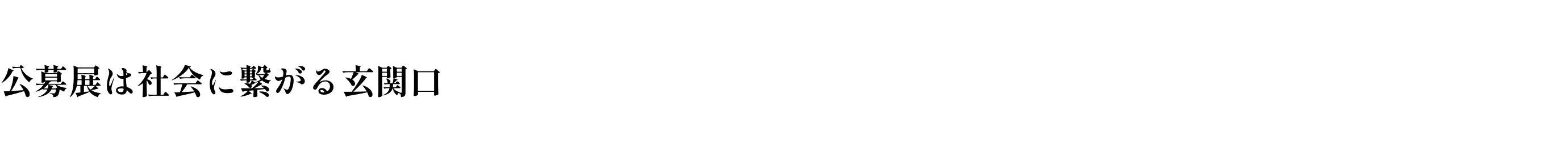
- 最後に、応募を検討しているアーティストの方へメッセージをお願いします。
- 「KOBE ART MARCHÉ」は、自分にとって「ひとつの玄関」のような存在だと思っています。
ギャラリーの扉を直接叩くよりも、ずっと気軽に社会とつながれる入口が用意されている感覚です。
公募展は、ピンポンダッシュくらいの気持ちでいいと思うんです。
深く構えすぎず、「とりあえずインターホンを押してみる」くらいの感覚で十分。
世界中にたくさんの公募展がありますが、押さなければチャンスは生まれません。
個人の制作活動とは少し切り離して、「社会につながる玄関」だと捉えて一歩踏み出してみると、思いがけず面白い体験が待っていると思います。
普段の活動ではなかなか出会えない人たちと、半ば強制的にコミュニケーションが生まれるのも、公募展ならではの魅力です。
まずは気軽に扉を叩いてみる。
その一歩が、次の展開につながっていくのではないでしょうか。

1995年生まれ。2018年日本大学芸術学部デザイン学科を卒業。個人の存在を未来まで遺すことをコンセプトに制作を続ける。ケビン・ケリーやレイ・カーツワイルなどの未来学者に影響を受け、人類の進歩とテクノロジーの進化が及ぼすメリットとデメリットを漠然とした未来像から写真を通して日常の光景へと現像する。外身と中身の構造を考察することで、人類がクローンやAIなどによって精神と肉体の関係から解放された次の人類の在り方を観るものに訴える。

